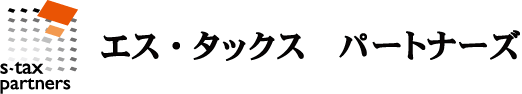- 東京地裁、法人の架空仕入れの計上を認定し、青色申告の承認取消処分及び法人税等の更正処分等を適法と判断(令和6年12月10日判決)。
本件は、電子部品の製造販売を行う法人である原告が、架空の仕入高を計上したなどとして青色申告の承認の取消処分及び法人税等並びに消費税等の更正処分を受けたことから、それらの処分の取消しを求めて争われた事案である。
仕入先A社の元代表は、東京国税局査察部の調査において、原告の代表者から架空の納品書、請求書、領収証等を作成すれば報酬を支払うと持ち掛けられ、それに応じたこと、別の会社からの仕入にA社を介する架空の伝票類を作成したこと、A社が原告から架空の開発研究を受託する契約書等の書類を作成したこと等を供述していた。
東京地裁は、本件各事業年度においてA社はすでに休眠状態にあったこと、仕入高の支払原資とされたS社からの借入金が客観的に原告に存在していないこと、原告と他の取引先との仕入、販売、在庫の個数の整合性からもA社からの仕入は架空であると考えられることなどから、A社元代表の供述は信用できるものと認定した。
仕入先B社の代表も、原告の代表者から、O社の仕事を紹介する見返りに、架空取引を行いその代金をバックするよう依頼されたこと、O社から受注した検査業務を原告から受注したように仮装することを指示されたと供述している。そして、原告から支払われた代金をM社のH氏の協力を得てM社に送金し、M社から受け取って原告の代表者に渡していたと述べている。
東京地裁は、H氏の供述内容がB社の代表の供述内容と一致していること、M社の口座の入出金の動きが両者の供述した資金の流れと一致していることなどから、B社の代表の供述も信用できると認定した。 東京地裁はこれらの認定事実から、原告の本件各仕入高等に係る取引は実体のない架空取引であると判断し、法人税法上、損金の額に算入できず、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額にも算入することはできないとした。
原告は、A社及びB社との取引を示す伝票や帳簿類を提出して、実体のある仕入であると主張したが、東京地裁は、それらの伝票類は原告代表が取引先に指示して作成させたものであると認定し、原告の行為は仮装・隠蔽にあたるとの判断を下した。その上で、これらの行為により青色申告の承認の取消事由があるとして、処分は適法と結論づけた。