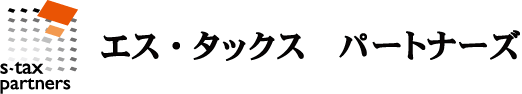- 原告が換価の猶予の担保として提供し、担保物処分のための差押えを受けた建物の公売公告処分が違法であるか争われた事件(令和6年11月29日判決)。
- 東京地裁、公売公告処分は滞納国税が換価の猶予に係る猶予期間の終期までに完済されなかったためであり、違法とはいえず。
本件は、担保物処分のための差押えを受けた建物について、原処分庁が行った公売公告処分が違法であるかが争われたもの。滞納会社の代表取締役を務めていた原告は、所有する建物①を担保として提供し、滞納会社に係る法人税等の滞納国税について換価の猶予を受けていたが、原処分庁は、猶予期間の終期までに滞納国税が完済されなかったとして、建物①を担保物処分のために差押えて(本件差押処分)、公売公告を実施した。なお、原処分庁は、滞納国税を徴収するために、滞納会社が所有していた建物②も差し押さえたが、滞納会社が差押えの解除を求めて任意売却申立書を提出したため、公売を中止している。
原告は、任意売却申立書を提出したのは、統括国税徴収官の「これで終わりにしましょう」という発言を信じたからであり、金策に奔走して原告自身が建物②の買請人となり、売買代金を滞納国税の納付に充てたにもかかわらず、滞納会社の滞納国税は完済されず建物①の差押処分がされたことは、徴収官による欺罔行為であると主張。公売公告処分は差押処分の違法を継承しているとして、取消しを求めた。
東京地裁は、原告が任意売却申立書を提出した当時、建物②は差押登記と公売公告がされていたから、原告が任意売却申立書を提出しなければ公売は中止とならず、そのまま公売されていたことが認められると指摘。しかも、公売されていた場合には任意売却よりも多額の滞納国税が未納のままになっていたことが考えられ、滞納国税が換価の猶予に係る猶予期間の終期までに完済されなかったことに変わりはないとした。その上で、差押処分は、滞納国税が換価の猶予に係る猶予期間の終期までに完済されなかったため、原告から担保として提供された建物①を差押えたのであり、処分は通則法(52条1項)及び徴収法(68条)の規定に従って行われたものであり、違法とはいえないとの判断を示した。
そのほか、東京地裁は、徴収官の原告に対する発言があったことを認める的確な証拠はなく、仮に発言があったとしても、原告が発言を信頼したことにより経済的不利益を受けることになったものではないとの見解を示した。