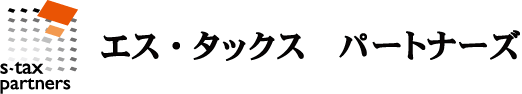- 訴訟上の和解により支払われた解決金が遺留分減殺請求に基づく価額弁償金に該当するか争われた裁決(令和6年7月3日裁決)。
- 審判所、解決金の全額が遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であると認めることはできないことから、更正の特則の要件(相法35条③一)は満たさないと判断し、原処分の全部を取り消し。
本件は、訴訟上の和解が成立し請求人に支払われた解決金が遺留分減殺請求(相続は令和元年7月前に発生)に基づく価額弁償金に該当するか争われた事案である。
請求人は、被相続人の公正証書遺言は無効であるなどとして兄を被告として訴訟を提起したが、裁判所の和解案に応じることとし、兄から請求人に対し解決金が支払われることになった。その後、請求人は遺留分減殺請求に基づく価額弁償金を取得したとして、解決金の一部について相続税の申告を行ったが、原処分庁は、解決金の全額が被相続人の相続財産に対する遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であって、当該金額のうち請求人の相続税申告において課税価格に含まれていなかった金額を課税価格に算入する旨の更正処分を行った。これに対して請求人は、更正処分において課税価格に算入された金額は遺留分減殺請求に基づく価額弁償金を超過する金額であって、損害賠償金に該当するものであるから相続税の課税価格に算入されないなどとして原処分の全部の取消しを求めたものである。
審判所は、訴訟の和解調書には解決金が遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であることを示す記載はないから、解決金の法的性質を判断することはできないとした。また、請求人は、訴訟において予備的請求として遺留分減殺請求を主張しているが、主位的には公正証書遺言は無効であることを前提として、本件相続の法定相続分に応じて被相続人の財産を相続したと主張していることから、予備的な主張を根拠にして解決金の全額が遺留分であると判断することもできないとした。加えて、解決金の算定根拠に関する双方の弁護士の申述等の内容も、X弁護士は、裁判官が損害賠償請求もしている兄妹間の関係をも考慮し、遺留分額を超える金額として算出されたものとしている一方、Y弁護士は、請求人の損害賠償請求は認定されなかったが、解決金には遺留分に係る遅延利息相当額が含まれているとしている。
これらのことからすると、審判所は、解決金の中に、請求人の遺留分減殺請求に基づく価額弁償金が含まれていること自体は認められるものの、訴訟の担当裁判官が、解決金のうちどの部分を遺留分減殺請求に基づく価額弁償金とし、どの部分をそれ以外の性質のものと考えていたのかは定かではないと指摘。したがって、少なくとも解決金の全額が遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であると認めることはできないとした。
その上で審判所は、原処分は相続税の法定申告期限から5年経過後に行われているため、原処分が適法に行われたといえるためには、更正の特則(相法35条③一)の要件を満たす必要があるとした。しかし、更正処分により増加した金額は遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であると断定できないことから、更正の特則の要件は満たさないとして、原処分の全部を取り消した。